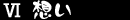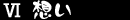
「カチャッ・・・」
動かなかった部屋の空気が動いた始まりだった。
「キィ・・・カチャッ・・・」
誰かが入ってきた。この部屋の主ではない、誰かが・・・。
「ふぅ、誰も居ないみたい。よかった。」
「さて、一応お邪魔します。」
声の主は、少女だった。
先日、普通ではありえない体験をした少女だ。
そう、人間が化け物になり殺されそうになった。
しかし、二人いた化け物の片方に助けられた。
少女、本人の意思に関わり無く危険な物語に入り込んでしまった。
少女の名は、梓と言う。
「こんなもんかな??」
梓は、リュックに服とか隼人に言われた物を詰め込んでいた。
隼人が、的確にそれぞれの場所を教えてもらっていたので、
梓はあまり迷わず、目当ての物を探し当てれた。
「早く、隼人の元に帰ろ。もし、誰か来たら大変な事に・・・」
と言いかけた時、玄関の向こうに人の気配がした。
「!!」
梓の体は、強張った。
石のように動かなくなる。
「ピッンポーン」
「すみませんー、新聞の集金ですけど・・・」
この声を聞いた時、体の緊張は解けた。
(集金か、よかった。でも、出て行けないな。居なくなるまで。)
暫くしてから、玄関の外に人の気配が完全に無くなってから、
梓は、ドアを開けた。
「居ないよね?誰も?」
目でもう一度、確認してから外に出た。
ドアにカギを掛け、急いで道に出ようとした時、声を掛けられた。
「おい!お前!なぜ、その部屋から出てきた!!」
サングラスをした、大きな男だった。
見張っていたのだ。隼人の部屋を。
梓の体が、考えるより先に動いた。
足は、地面を蹴っていた。
男は、追いかけてくる。
いくら、梓の方が先に走り出したといえ、その差はすぐに縮まっていく。
(ハァ、ハァ、どうしよう?)
考えがまとまらない。
気が付いたら、結構人がいる通りに来ていた。
(あっ、そうだ!!)
梓は思いついた事を実行した。考えている暇などないのだ。
「助けて!痴漢が追いかけてくるの!」
走りながら出来るだけ大声で叫んだ。
もう、呼吸が出来ないくらいに張り叫んだ。
「なんだ?なんだ?」
人々の関心が集まってきた。すかさず、梓は近くにいた人に
「あの男、痴漢が私を追ってくるの!助けて!」
そう言いながら追いかけてきたサングラスの男を指差した。
人々の視線は一斉にその男に向けられた。悪意のある視線で。
驚いたのは、男の方である。突然、痴漢扱いにされてしまったのだから。
男の方に人々が群がっていく。男を取り囲むように。
(やった、今のうちに逃げれる)
今、ここにいる人は男の方に注目している。
梓は、気付かれないようにこの場から逃げた。
とにかく、一秒でも速く。隼人のもとへ。
それだけを考えながら。
トントン・・・
部屋のドアがノックされた。
「んっ?梓か?」
ドンドン!
更に激しく叩く。
「わかった。今、開けるから待ってろ!」
隼人は、鍵を外す。それと同時に梓が倒れ込むように入ってきた。
「おい、どうしたんだ?何かあったのか?」
梓に荷物を取りに頼んだ。しかし、今の梓は疲れきっていた。
全力疾走して来たみたいに肩で息をしている。
そして、顔色が真っ青だ。
とにかく、何かあったのは確かだ。それくらいはわかる。
「こっちに来て休め。話はそれから聞く。」
そう言って、梓を抱き上げてベットの上に降ろす。
そして、冷蔵庫からミネラルウォーターを差し出す。
「飲むか?」
「えっ?あっ、うん。ありがとう。」
ペットボトルを受け取って、一気に乾いた喉を潤した。
隼人は、そんな梓の横に腰を下ろした。
暫らくは、静かな空気が流れていた。
それを破ったのは、隼人だった。
「何があった?」
梓は、先程あった事を話した。大きな男が追いかけてきた事を。
「・・・ちっ、もうあいつらの手が回って来てたか?悪かったな、怖い思いさせて」
隼人は、梓の髪を優しく撫でた。
その途端、梓の大きな瞳から涙がこぼれ落ちた。
「うぅっ、怖かったよ〜」
緊張の糸が切れたのであろう。梓は隼人の胸の中で泣き出した。
「よしよし、もう怖くないから。今度から俺が守ってやる。どんな時も、どんな時でも。」
隼人は、優しく梓の髪を撫でている。彼女が眠りに落ちてからも。
「俺が守るから。もう、怖い思させないように俺が守る、梓を。」
誓いを立てるように。
しかし、隼人の声は眠りの世界に落ちている梓には聞こえなかった。